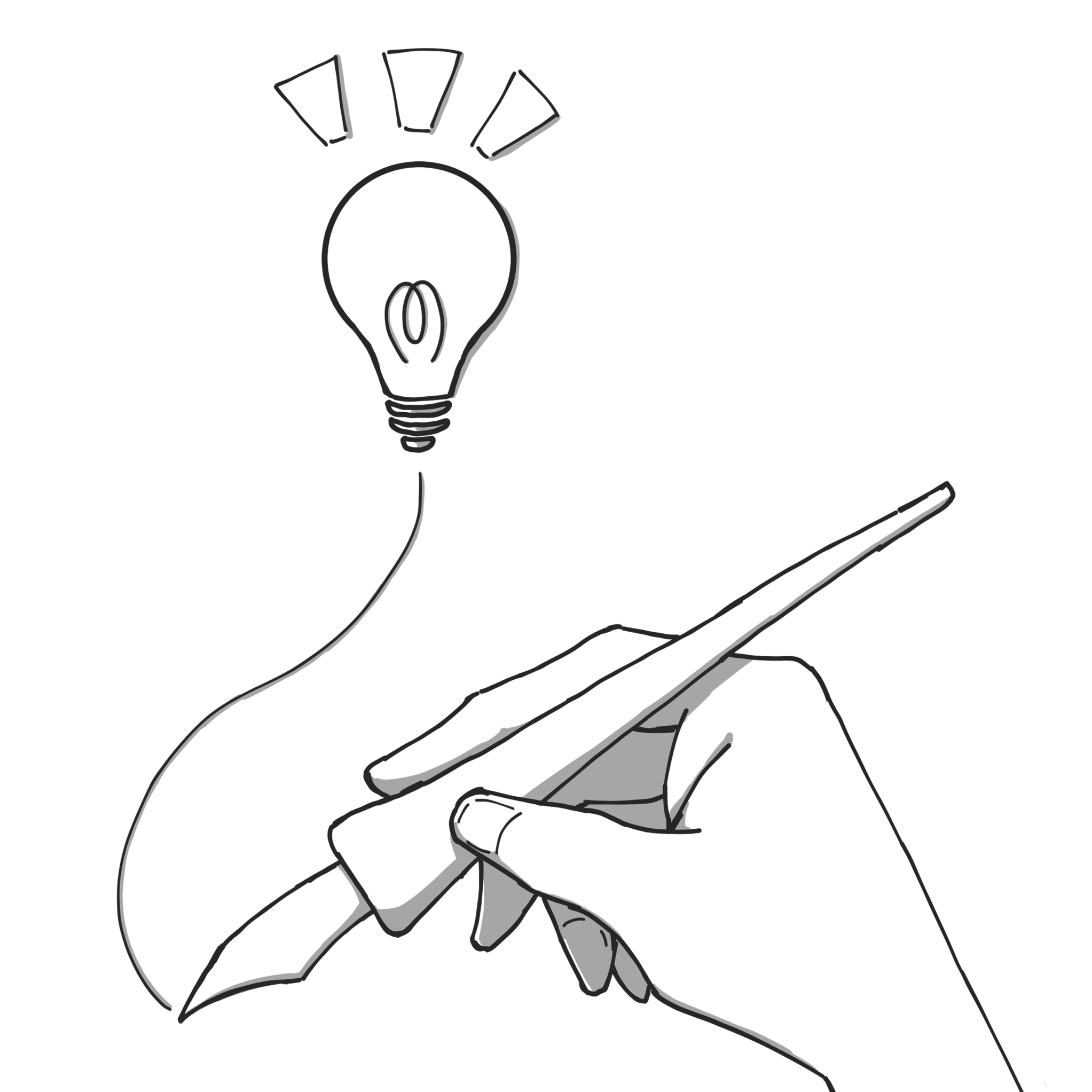「仕事に行きたくない」と感じながら出社している方は少なくありません。気分は乗らないけど社会人としてしっかりしなければーーーそんな気持ちで何とか乗り切っているのではないでしょうか。
本記事では「仕事に行きたくない」気持ちが生まれる理由や効果的な対策について、科学的な視点も交えながら解説いたします。また、転職を検討した方がよいケースも紹介していますので、合わせてご覧ください。
目次
「仕事に行きたくない」は当たり前の感情
厚生労働省の「令和4年 労働安全衛生調査(実態調査)」によると、社会人の82.2%が仕事に関して強い不安・悩み・ストレスを感じていることがわかりました。こうした感覚は「仕事に行きたくない」気持ちにもつながっており、多くの社会人が当たり前に感じている感情です。
強い不安・悩み・ストレスを感じている主な理由は下記の3つです。
- 仕事の量
- 仕事の失敗、責任の発生
- 仕事の質が合わない
とくに「仕事に行きたくない」という感情につながっているのは仕事の内容です。自分の能力に見合わない仕事を抱えていたり、残業が続くなど過酷な状況では、心身の健康が損なわれやすくなります。このような状態が続くと、出社への意欲が低下することも珍しくありません。
40代以上の中堅・ベテラン社員では、職場での責任や期待が増すことで、強いストレスを感じる傾向があります。部下の管理や成果へのプレッシャーが負担となっているケースが多く、「仕事に行きたくない」感情を強めています。
他にも、人間関係も要因となっています。上司や同僚とのコミュニケーションが上手くいかないと感じている社員は慢性的な不安やストレスを抱えており、「仕事に行きたくない」と感じやすい傾向にあります。人間関係の悩みは、とくに若手社員に顕著だといえるでしょう。
ストレスなく仕事をしてる人は2割
「仕事に行きたくない」と感じる社会人がいる一方、ストレスなく仕事をしている人も存在します。2割ほどの社会人が仕事に対してポジティブな感情を持って出社しています。
では、「仕事に行きたくない」と感じる人とストレスなく仕事をしている人の違いは何なのでしょうか?実はストレスなく仕事をしている人は、下記の4つの要素のどれか、または複数を生活の中で実践しています。
- 仕事にご褒美を用意している
- 職場に楽しみがある
- 仕事をゲームとして楽しんでいる
- 職場以外に自分らしく過ごせる居場所がある
「仕事に行きたくない」と感じている人の場合、上記の要素を生活の中に取り入れていない人も多いのではないでしょうか。
もちろん上記の要素を実践しているからといって、「仕事に行きたくない」気持ちが100%消えるとは限りません。ですが実践した場合、「仕事に行きたくない」気持ちが解消される可能性もありますし、軽減されることもあります。
「仕事に行きたくない」気持ちで過ごしている場合、実践できそうな要素から取り組んでみることをおすすめします。上記の要素についての解説と実践方法については、「仕事に行きたくないへの対策4選」で解説しています。
「仕事に行きたくない」は甘え?
結論から書くと、「仕事に行きたくない」気持ちはまったく甘えではありません。むしろ仕事への向き合い方を考える大切な感情であり、しっかりと向き合う必要があります。
よくあるのが、「仕事に行きたくないのはみんなが思ってるんだから我慢するのが当たり前」といった意見です。確かに「仕事に行きたくない」と感じている社会人は多いですし、仕事には我慢が必要な部分もあります。ですが、出社に強い抵抗感が出ている状態は健全ではありません。
実際、2割ほどの社会人はポジティブな感情で出社しており、こうした人たちは活き活きと仕事に取り組んでいます。仕事は人生の多くの時間を占める活動ですし、健全な形で取り組むのが理想でしょう。
ですので、「仕事に行きたくない」気持ちがあっても、甘えなどと考えて感情を押し殺すことは間違っています。何が原因なのかしっかりと向き合い、対処するようにしましょう。
「仕事に行きたくない」と感じる4つの状況
ここからは、「仕事に行きたくない」と感じる具体的な状況について解説します。
- 休み明けで気分が乗らない
- 人間関係でストレスを感じる
- 仕事がつまらない・やりがいを感じられない
- 身体的・精神的に疲れている
上記4つの状況で、多くの社会人が「仕事に行きたくない」と感じています。それぞれについて見ていきましょう。
休み明けで気分が乗らない
休み明けに仕事への気分が乗らないのは、生活リズムの変化が主な原因です。とくに長期休暇は遅寝遅起きの習慣が定着しやすく、朝起きた時に体内時計が乱れて気分が乗らない、といった状況になりがちです。
また、休暇中の楽しい経験などが仕事への憂鬱を増幅させることもあり、「仕事に行きたくない」と強く感じさせてしまうケースもあります。
人間関係でストレスを感じる
すべての問題は人間関係に辿り着くといった言葉があるように、職場の人間関係は出社意欲に大きく関係しています。上司・同僚との関係性が良くなかったり、パワハラやモラハラの被害を受けているなどのケースです。
他にも、職場そのものがギスギスしている、人間関係について相談できる相手がいない状況も「仕事に行きたくない」原因になることがあるでしょう。こうした職場環境は不安やストレスを感じやすく、心と身体の調子を崩す原因にもなりかねません。
仕事がつまらない・やりがいを感じられない
つまらない・やりがいを感じない仕事への興味を失わせ、「仕事に行きたくない」と思わせる原因になります。主なケースは次のようなものです。
- 単調な業務の繰り返し
- 成長が評価されない
- 思っていた業務と違った
それぞれを見ていきましょう。
単調な業務の繰り返し
脳科学の研究によると、刺激の少ない環境ではやる気をうながすドーパミンの分泌が減少することがわかっています。単調な業務が原因でやる気を低下させ、「仕事に行きたくない」と感じる原因になる場合があります。
成長を評価されない
とくに若手社員は企業や上司から認めてもらいたい気持ちが強い傾向にあります。そのため、成長を適切に評価されないと自己肯定感が下がり、仕事への意欲がなくなって「仕事へ行きたくない」と思うようになる場合があります。
思っていた業務と違った
とくに適性ではない業務を担当している場合、強いストレスとなり出社への抵抗感を強めてしまいます。また業務量が極端に多かったり、逆に少ない場合も不満を感じ「仕事へ行きたくない」と感じてしまう原因になります。
身体的・精神的に疲れている
全国10万人を対象にした日本リカバリー協会の「日本の疲労状況2023」によると、慢性的に疲れている国民は38.6%いることがわかりました。慢性的ではないにしろ、疲れを感じている国民は39.9%おり、合わせると78.5%の国民が疲れを感じている計算になります。疲れの理由はさまざまですが、8割弱の国民が疲れを感じているのは多いといえるのではないでしょうか。
仕事における身体的・精神的な疲れの原因としては、長時間労働や業務のミスマッチ、人間関係のトラブルなどが挙げられます。
具体的な症状としては、頭痛や胃痛といった身体症状や、集中力や判断力の低下といった脳のパフォーマンスの低下などがあります。その結果、仕事で思うように成果が上がらなくなり、ストレスを抱えて悪循環に陥るケースも少なくありません。
身体的・精神的な疲れから仕事へのモチベーションを失い、「仕事に行きたくない」と感じる人は多いものです。
「仕事に行きたくない」気持ちを放置するとどうなるのか
「仕事に行きたくない」気持ちを放置して最初に出るのは、仕事のパフォーマンスの低下です。集中力・思考力やモチベーションが低下し、仕事の質が悪くなったり、思うような成果が出ないといった状態になります。
また「仕事に行きたくない」気持ちを我慢すると職場の人間関係も悪化しやすくなります。上司・同僚とのコミュニケーションが減少し、孤立感が強まることでチームワークに支障が出る場合もあり、仕事への不満がさらに高まることも考えられます。
中長期的にはメンタル疾患のリスクも高まります。うつ病・適応障害をはじめ、パニック障害や自律神経失調症などが考えられ、最終的には長期休職や退職を余儀なくされるケースも少なくありません。
「仕事に行きたくない」気持ちを甘えととらえる人も多いですが、深刻な状態の前触れかもしれませんので、軽く考えないようにしてください。
「仕事に行きたくない」への対策4選【科学的】
では、どうしたら「仕事に行きたくない」と思う気持ちと上手に付き合えるのでしょうか。
- ご褒美を設定する
- 職場で楽しみを見つける
- 仕事をゲーム化する
- 触媒以外の居場所を見つける
ここでは、科学的な内容を含め、上記4つの対策について解説します。
ご褒美を設定する
ご褒美を用意するとドーパミン(やる気ホルモン)の分泌が促進されるため、仕事へのモチベーションを高める効果が期待できます。
その際に重要なのは、具体的な目標とご褒美を設定することです。例えば「今週の〇〇のタスクを期限内に達成できたら、週末は好きな映画を楽しむ」といった明確な報酬です。
中長期的な目標には、より大きなご褒美を設定するとよいでしょう。「数ヵ月に及ぶこのプロジェクトを成功させたら、欲しかったバッグを買う」といった報酬はモチベーション維持につながります。
ただし、ご褒美は無理のないものに設定するようにしましょう。仕事のストレス発散を目的に、暴飲暴食や大量に買い物をするといった行為はNGです。依存症にもつながるため注意してください。
職場で楽しみを見つける
職場に楽しみがあることも、仕事へのモチベーションを高める効果があります。職場の楽しみの種類には人間関係と環境があります。
人間関係では、上司・同僚との良好な関係作りが挙げられるでしょう。休憩やランチタイムでのコミュニケーションを増やすことで一体感ができ、話す楽しみが生まれます。些細な会話からでもよいので、さりげなく話しかけてみるのが効果的です。
環境では、例えば業務の間に好きな音楽を聴いたり、デスクに観葉植物を置くなど、働きやすい環境にすることが効果的です。もちろん社内規定で問題ない範囲にすることは必要ですが、自分好みの環境作りができれば、職場に来る楽しみを1つ増やすことができます。仕事への前向きな気持ちも芽生えやすいでしょう。
仕事をゲーム化する
仕事をゲーム感覚で捉える方法は、「仕事に行きたくない」気持ちへの効果的な対策になります。「ゲーミフィケーション」と呼ばれるこの方法は、モチベーションと意欲をキープするためのテクニックとして知られています。
具体的には、1日の業務をチェックリスト化し、完了するごとに得点を付ける方法が簡単でおすすめです。1つ業務を達成するごとに脳内でドーパミンが分泌され、次の目標に向かう意欲が自然と湧いてきます。タスク管理アプリを活用して、進捗を視覚化することもよいでしょう。
また、適度な競争を取り入れることも効果的です。例えば同僚をライバルキャラクターに見立て、競い合いながら業務にあたると楽しみながら取り組めるようになります。ただし、勝利だけが目的になるとストレスの原因になるため、競争にのめり込み過ぎないよう注意してください。
職場以外の居場所を見つける
「サード・プレイス」と呼ばれる職場以外の居場所を見つけることは、仕事で溜まったストレスの解消や精神を安定させる意味で効果的です。職場以外で人と交流できる場を持っておくと、心身をリフレッシュさせることができるでしょう。
例えば、SNSでつながった趣味仲間との交流や、地域のコミュニティ、習い事の教室といった場所が挙げられます。こうした新しい環境での交流は、視野を広げ、職場での問題やトラブルから一旦距離を取り、冷静に見つめ直す機会になります。
また職場以外のつながりを持つことで、孤独感やストレスが軽減され、再び仕事と向き合うための活力を養うことにもつながります。誰かと話したり一緒に何かを楽しんだことでスッキリし、悩みが小さくなった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
転職を検討した方がいいケース
中には、どんな対策をしても解消できない「仕事に行きたくない」状態もあります。そのような場合、転職の検討も必要になるため注意しなければなりません。
- 心と身体の調子を崩している
- 人間関係が悪い
- 働く意義がわからない
ここでは、上記3つの転職を検討した方がいいケースについて解説します。
心と身体の調子を崩している
心と身体の調子を崩した状態が続いている場合、転職を検討する必要があります。
心と身体の調子が崩れているサインとしては、涙が止まらない、眠れない、食欲がないといった状態が挙げられます。他にも、めまいや頭痛、動悸や胃腸の不調など身体的な症状として表れるケースもあるでしょう。
こうした状態を長期間放置すると、うつ病や適応障害、その他のメンタル疾患につながる可能性があるため注意しなければなりません。これらの症状が現れたら、心療内科を受診することも検討してください。
転職活動を始める場合も、まずは心と身体のコンディションを向上させることを優先し、無理のないペースで始めることが大切です。
人間関係が悪い
修復できないほど職場の人間関係が悪い場合も転職の検討が必要です。コミュニケーション不足や意見の不一致、ハラスメントなどが続くとストレスが蓄積し、うつ病や適応障害といったメンタル疾患を引き起こすこともあるため放置してはいけません。
また人間関係の悪さが仕事へのモチベーションを低下させ、業務に影響を及ぼすこともあります。相性の悪い同僚や上司との関係がストレスとなり、集中力が欠けてミスが増え、生産性が低下するといったことはよくあります。
職場環境に関しては、個人の力では改善できない状況も多いものです。そのような場合は一刻も早くその職場を離れることも、健全に働く上で重要です。
働く意義がわからない
働く意義がわからなくなると仕事へのモチベーションが急激に低下し、成長や貢献といったポジティブな感覚も感じられなくなります。こうした状況になると人は消極的になり、給料をもらうためだけに惰性で働くようになりかねません。
このような状態で長く働いていると、自己肯定感が低下したり希望を失うといった深刻な状態になるケースもあります。うつ病などのメンタル疾患につながる可能性もあるため、注意しなければなりません。
仕事の意義が見えないと感じる場合、まずは自己分析を行って自分の価値観を明らかにすることが重要です。自分が大切にしている価値観をもとに、目指したいキャリアの方向性を明確にすることで、今後の展望が見えてきます。
下記の記事で仕事の価値観の見つけ方について解説していますので、併せてご覧ください。
「仕事に行きたくない」気持ちは適切に対処しよう
「仕事に行きたくない」という気持ちは、社会人の8割が経験する感情です。休み明けの気分の低下、人間関係のストレス、仕事がつまらない・やりがいがないなど、その原因は人によってさまざまです。
よくあるとはいえ、「仕事に行きたくない」気持ちをを放置すると、メンタルの不調や仕事のパフォーマンスの低下につながる可能性があるため注意してください。本記事で紹介した対策を活用してもらい、「仕事に行きたくない」気持ちと上手に付き合っていただければと思います。